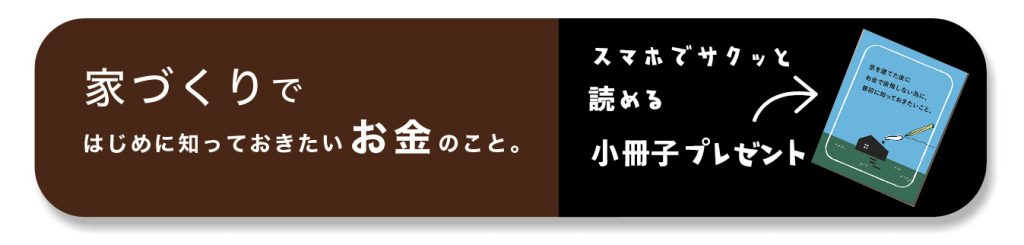両親の退職・子どもの小学校進学のタイミングで、二世帯住宅にして同居を考えているご家庭は少なくありません。
共働きで忙しく働く子育て世代にとって、子どもの世話を助けてくれる両親との同居はメリットも大きいでしょう。しかし実際には、ライフスタイルの異なる世代間の同居にはデメリットもあり、ストレスなく暮らせるか不安ですよね。
二世帯住宅を始める前に、お互いが暮らしに求める条件の話し合いが大切です。適切な距離感を保つことでデメリットを解決し、メリットをより大きくできます。
本記事では、子育て世代が二世帯住宅で親と同居するときのメリット・デメリット、二世帯住宅の間取りやデリケートなお金の問題についても、詳しく解説します。ライフスタイルに合わせた二世帯住宅で、家族みんなが幸せに暮らせる家づくりを実現しましょう。
Contents
子育て世代が二世帯住宅で暮らすメリット

二世帯住宅とは、親世帯・子世帯が生活を共にするための住宅をいいます。
親の退職や介護の必要が出てきたタイミングで、同居や二世帯住宅を検討することが多いようです。あるいは子世帯で、戸建て住宅への引っ越しがきっかけになるケースもあります。
子どもが生まれて広い部屋が必要になる、あるいは転校しなくてもよいように、小学校に上がる前にマイホームを持ちたいと考えるからです。ここでは、子育て世代が二世帯住宅にしたときに考えられるメリットを解説したいと思います。
子どもの世話をしてもらえる
近年の子育て世代は、子どもの人数に関わらず共働きのご家庭が多いでしょう。育休・産休制度を利用しても、子どもが幼い内から両親いずれも仕事をしているため、日中はいっしょにいられない状態になります。
親世帯(祖父母)が健康な場合、保育園に預けたとしても緊急時のお迎えや日常の送迎を助けてもらえるケースが多く、頼りになるのではないでしょうか。
小学校にあがると、より問題は複雑になります。
急な残業で指定時間に迎えに行けない場合は、保育園では延長保育で対応してもらえるでしょう。しかし、小学生の子どもを預かってくれる「学童保育」は終了時間が早く、その頃には時短勤務が使えなくなる企業が多いのが現状です。
そのため、親(特に母親)が働き方の変更をせまられる、いわゆる「小1の壁」問題が起こります。現状では女性が転職・退職をする場合が多いものの、ダイバーシティを進める企業が増えたため管理職のワーキングマザーも増えてきました。
子どもが親の帰宅時間まで一人で過ごせる年齢になるまでは、送迎や学習補助をしてくれる存在が近くにあるのは安心ですし、キャリアへの影響も減らせます。
生活面でのサポートがある
子育てだけでなく、日常的な買い物や食事・家事のサポートを受けやすくなる点もメリットといえます。
両親との関係性にもよりますが、二世帯住宅で暮らす親子はお互いにサポートし合う傾向が高いのではないでしょうか。共有部の清掃や庭の手入れ・宅配便の受け取りなど、些細なことでも代わりに請け負ってくれる人がいると、精神的な負担も少なくなりますよね。
しかし役割分担は、あらかじめしっかり決めておくことが大切です。
どちらかが過剰な負担を強いられるとストレスが溜まり関係性が悪化して、デメリットに転じる可能性も考えられます。お互いが気持ちよく助け合える環境を作ることが、二世帯住宅での課題です。
世代を超えた交流のなかで学びを得られる
都会暮らしでは、高齢者との関わりは少ないのではないでしょうか。祖父母と近い場所で生活することで、伝統的な地域の行事に参加する機会を増やせるという話も聞かれます。情緒を育て、学びを得る機会となり、子どもの成長を促すよい機会となるでしょう。
子育て世代が二世帯住宅で暮らすデメリット

二世帯住宅は親と近い暮らしができるため、子どもの世話や日常的なサポートを受けられるなどのメリットがありました。しかしデメリットもあるため、きちんと理解して事前に解決できる問題かどうか検討しておきましょう。
生活習慣の違いによるストレス
リタイア後の親世帯と仕事や子どもの生活がある世帯では、起床・就寝時間の違いなど生活の時間帯がずれやすくなります。間取りによっては、生活音がお互いのストレスになる可能性も考えられます。
また親が子育てをしていた時代と現代では、ライフスタイルや考え方に違いがあるでしょう。お互いが持っている「当たり前」の価値観のズレが原因で、思いもよらないいさかいに発展するかもしれません。間取りや設備で解決できることもあるので、計画段階からしっかりと話し合いましょう。
子育てへの過干渉
子育てや教育方針については、親子でも違いがあるのが常です。
親(祖父母)の価値観で子ども(孫)に行き過ぎた発言や対応をされても、金銭面や生活面でサポートをしてもらっているからと強く反論できずに困ることも考えられます。親(祖父母)もよかれと思い言っていることもあり、反論や意見をいうことにも遠慮がちになる側面もあります。子ども(孫)もおじいいちゃん・おばあちゃんと両親の言い分が異なり、困惑したり傷いたりする事態になりかねません。
ライフスタイルの違いと同様に子育ての方針についても、あらかじめ親にしっかり伝えた上で、協力をあおぐようにしてくださいね。また自分たちの意見を通すだけでなく、子育ての先輩としての意見を尊重し、素直にアドバイスを受け入れる寛容さを持つことも大切です。
プライバシーが守られにくい
二世帯住宅は基本的に、24時間二つの家族が近い場所で生活する状態となります。そのため離れて暮らしているときよりも、プライバシーが守られにくいデメリットもあります。
お互いにそのつもりはなくても、監視されている気持ちになってしまうかもしれません。根本的な解決は難しいかもしれませんが、間取りによっては避けられることもあるので、人の目を気にしがちだと感じる方は特に、設計時点で相談することをおすすめします。
親が同席しているときに言い出しにくい内容は、別席で設計士や営業担当者に伝えて対応してもらうようにしてください。住まう人が快適に暮らせるように、配慮した計画をしてもらえるでしょう。
二世帯住宅の3つの間取りと特徴

子育て世代のとって二世帯住宅は、メリット・デメリットをあわせ持つ住まいです。デメリットをできるだけ解消し双方が気持ちよく暮らせる間取りで、メリットを生かした二世帯住宅を設計したいですよね。
二世帯住宅のタイプ的には、次に紹介する3種類の形があります。それぞれの良い点・悪い点を踏まえて、ご家族にとって快適な二世帯住宅のかたちを検討してください。
完全同居型
玄関・リビング・ダイニング・キッチン・水回りなどを共有した間取りです。
共有部のほかには親世帯・子世帯それぞれの寝室や子ども部屋が用意されますが、常にお互いの気配を感じられ、まさに「ひとつ屋根の下」に暮らしている状態となります。祖父母と子ども(孫)との交流が図りやすく、のちのち同居する家庭よりも絆を深められるでしょう。
子育ても祖父母を含めた家族全員で行う感覚が強くなる一方で、プライバシーは守られにくいデメリットがあります。義両親との生活はお互いに気を遣いあうシーンも多く、場合によってはストレスを感じやすいかもしれません。また光熱費を含む生活費が共同となるため、費用負担の別をはっきりさせておき、トラブルを防ぎましょう。
部分共用型
玄関など一部の設備を共有しながらも、生活空間は各世帯にそれぞれ設けるかたちです。
1階・2階で分けられるケースが多く、それぞれの気配を感じながらも適度にプライバシーが守られます。キッチンや浴室・洗面・トイレなどの水回り設備が、世帯ごとに独立しているため、生活時間帯がずれても使いやすいでしょう。玄関が同じなので、子どもたちが学校から帰宅したときも祖父母が気づきやすく、親が不在でも安心です。
部分的に共有している場所があることで電気代などの光熱費負担の振り分けが難しい点や、将来的に二つの設備が不要になるなどのデメリットもあります。また設備が二つずつ必要になる分、建築費用が高くなります。
完全分離型
同じ建物内に暮らしていますが、玄関をはじめとしたすべての設備を分けた間取りの二世帯住宅を指しています。
部分共用型と同様に、1階・2階で分けられるパターンがほとんどで、メゾネットタイプのマンションをイメージすると分かりやすいでしょう。2階の世帯は隣り合った玄関から入り室内階段で上階へあがるか、外階段で2階に設けた玄関から室内へ入る間取りになります。
完全に生活を分けているためプライバシーは守りやすく、いざという時はコミュニケーションを取り、お互いをサポートしやすい環境です。光熱費や生活費も完全に分けることができるため、費用負担の問題は解決できます。
しかし子どもが帰宅したときも気づきにくく、完全同居型・部分共有型に比べると相互サポート力はさがってしまいます。また、部分共用型と同じように設備が各世帯に必要なため、建築費用が高くなります。
二世帯住宅を建てるときに話し合うべき「お金」のこと

二世帯住宅の設計では、親子間での話し合い・相互認識のすり合わせがとても重要です。日常的な暮らしのなかで起こるストレスや、価値観のちがいを埋めるだけでなく、トラブルの原因になりやすい「お金」についても明確に決めておくべきでしょう。
厳格なルールを定めるとかえって疲れてしまうため、双方で妥協できるゆとりを持つのも大切です。ここでは、二世帯住宅における「お金」について、あらかじめ知っておくとよい情報をまとめたいと思います。
建築にかかる費用はだれが払う?
もっとも重要なのは、「建築費用」です。
土地は親名義で元々所有している場合が多く、主に数千万円以上かかる建築費用の負担割合について考えなければなりません。もちろん新たに土地を購入する際は、その費用も加算されます。
まず費用の出資パターンとして考えられるのは、次のとおりです。
- 親世帯が全額
- 子世帯が全額
- 親世帯・子世帯で分ける
「完全分離型」の二世帯住宅であれば、それぞれの世帯の分を支払えます。しかし「完全同居型」「部分共用型」では、共同で支払う流れが一般的でしょう。頭金は親世帯が出して残額は子世帯がローンで支払う、親子リレーローンを利用するなどのケースがあります。
現時点で親の収入が多いとしても、将来的には子世帯が多くなる可能性が高く、双方にとって無理のない返済プランや費用負担の割合を考えなければなりません。また共同出資の場合、所有権の名義によっては贈与税がかかることもあるため注意が必要です。
詳しくは専門家に相談して、適切な判断をあおぐようにしてください。
補助金を活用して負担を軽減しよう
親子で分割支払いをして、それぞれの世帯にかかる建築費用を抑えられたとしても、家づくりにかかる費用は莫大です。二世帯住宅を建てる人向けに、国や自治体の補助制度があるので活用してみてはいかがでしょうか。
たとえば空間工房LOHASのある静岡県・富士市には、次のような支援制度があります。
- 多世代同居・近居支援奨励金
「子育て世代の負担軽減および高齢者の安全・安心な暮らしの確保を図るため、多世代であらたに同居・近居するための住宅取得またはリフォーム工事」に対する補助制度のこと。(記事公開時点/出典:富士市ホームページ)
また二世帯住宅に限らず、新築あるいはリフォームによる家づくりの補助制度があり、多世代同居により補助金が上乗せられるケースもあります。国土交通省の「すまい給付金」や「地域型住宅グリーン化事業」などを参照してみてください。
他にも様々なサポート制度があるので、調べてみましょう。細かな条件や期限など、素人では分かりにくい点もあるため、家づくりを依頼する業者や専門家に相談するとよいでしょう。
生活に関わる費用をどう分けるか
生活に関わる費用を共有している場合の負担割合も、考えなければなりません。間取りによっては、光熱費を分けて計算できないケースもあります。メインで親が支払い、子世帯は月々決められた金額を親へ払うなどの方法をとってもよいでしょう。
きっちりと分けるかどうかは、双方の性格によるところもあります。将来的な収入が親子で逆転することを加味して、柔軟に考えるようにしてください。
子ども(孫)の面倒をみるにあたり、親(祖父母)から食事やおやつを提供することもあると思います。しかし「孫のためだから」「ついでだから」と、費用に関してはなにも言われないパターンが多いのではないでしょうか。
逆もまた同様で、年齢を重ねて子世帯が親をサポートするタイミングも出てきます。お互いに気持ちよく二世帯住宅での生活を続けるためにも、金銭授受はなくても、尊敬と感謝の気持ちを謙虚に持つようにするとよいでしょう。
不安をとりのぞき、安心して暮らせる二世帯住宅を実現しましょう

子育て世代が親と二世帯住宅で暮らすには、さまざまなハードルや不安があるでしょう。二世帯住宅には、メリットもデメリットもあります。また家づくりには多額の費用が必要となるため、親子でもきちんと話し合い、決めていかなければなりません。
各家庭に向いている二世帯住宅の間取りや、費用に関わる問題はとても複雑で分かりにくいため、正解が見えづらいですよね。親身になってサポートをしてくれる専門家に相談しながら、安心して暮らせる二世帯住宅を実現させてくださいね。
空間工房LOHASでは、難しいお金についてもお客様に寄り添ってご相談を承っています。富士山周辺の車で1時間圏内での家づくりをお考えの方は、空間工房LOHASへご相談ください。
■直接いらっしゃらなくても、ZOOMでのオンライン家造りも可能です。気軽に家造りの進め方や、移住者支援の補償のこと。土地選びまでご相談にのっています。→ ご予約はこちら
■ 何かお家のことで質問があれば、お気軽にLINEでご質問ください→ こちら
■ ロハスのYouTubeチャンネル「工務店おじさん」では、
家づくりで後悔しないための情報や新築ルームツアーをUPしています→ こちら
チャンネル登録よろしくお願いします! →https://www.youtube.com/channel/UCsWmQpk-W6h6GkJOv0jH5Jg
■ インスタグラム ロハスの家 暮らしの工夫 → こちら
—-
富士市富士宮市で住むほどに健康になる注文住宅・木の家をつくる工務店
空間工房LOHAS(ロハス)
静岡県富士市荒田島町8-16
TEL:0545-57-5571
FAX:0545-57-5576
Email:lohas@fork.ocn.ne.jp
HP:https://www.kobo-lohas.jp
家を建ててからかかるお金で、
後から後悔しない為に、最初に知っておいて欲しい事をまとめました。
お読みでない方はこちらからご覧いただけます↓
今までで200棟住宅を建築してきたLOHAS社長の寺﨑が
「良い家造り」のために知っておくと必ず役に立つ話。
こちらから読んでみる↓